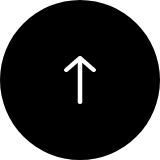本文
固定資産税について
1.固定資産税とは
固定資産税は、土地・家屋・償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納付する税金です。
2.納税義務者
固定資産税を納付する人は、原則として毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)現在、固定資産を所有している人です。
登記簿や課税台帳に所有者として登録されている人(償却資産については、償却資産課税台帳に所有者として登録されている人)が納税義務者となりますので、売買などで実際の所有者が変更されていても賦課期日現在、所有権移転登記等の名義変更手続きが完了されていなければ、旧所有者が納税義務者となります。
3.納期限
第1期 5月31日
第2期 7月31日
第3期 12月25日
第4期 翌年2月末日
納期の最終日が土日または祝祭日の場合は、その翌日が納期限となります。
4.税額の算出
土地、家屋、償却資産それぞれの課税標準額を合計し、1,000円未満を切り捨てた額に固定資産税の税率(1.4%)を乗じます。算出された額の100円未満を切り捨てたものが、年税額となります。
5.免税点
同一市町村内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合は、固定資産税は課税されません。
土地 30万円
家屋 20万円
償却資産 150万円
ただし、マンション等、区分所有物件の場合はこの限りではありません。
6.納税義務者が死亡した場合
納税義務者の方が亡くなられた場合、相続人の方が新所有者になります。このような場合、納税義務も引き継がれることとなりますので、「相続人代表者指定(変更)届出書」をご提出ください。
なお、相続人が2名以上おり、賦課期日までに相続関係が確定しない(相続人代表者指定(変更)届出書のお届けがない)場合は、相続人の共有名義として翌年度以降課税させていただきます。
また、未登記家屋について、相続・譲渡等により所有者が変更となった場合は、「家屋所有者変更届出書」を税務課資産税係まで提出ください。
土地・家屋の名義変更手続きに関しては、登記があるものについては、法務局での手続きになります。
(注)「遺産分割協議書」を作成済みの場合は「遺産分割協議書(写)」を、相続放棄されている場合は「相続放棄申述受理証明書(写)」を税務課資産税係まで提出してください。
7.納税管理人について
固定資産税の納税義務者が、町外に居住している等、固定資産税の納税に支障がある場合、「納税管理人」を定めることにより、納税義務者を変更することなく納税通知書等を納税管理人に送付することができます。
例えば、単身赴任等で固定資産税の納税義務者が町外に住所を移す場合、納税管理人を指定することにより、引き続き町内に居住する家族あてに納税通知書等を送ることができます。
納税管理人を定める場合は、「納税管理人申告書」を税務課資産税係まで提出してください。
8.地目が変更となった場合
土地は、原則として賦課期日現在の現況地目によって評価額、課税標準額が決定され、課税となります。随時調査しておりますが、確認できない場合は、現況と異なる地目での課税となってしまいますので、現況地目を変更されましたら税務課資産税係までご連絡をお願いします。
9.家屋を取り壊した場合
新築・増築による既存家屋の取り壊しや、老朽化等の理由で家屋を取り壊した場合には、税務課資産税係までご連絡をお願いします。現地確認を行った後に、家屋の滅失として処理し、次年度より課税されなくなります。
(注)家屋を取り壊した場合、当該地番の土地の課税標準額が変動する場合がございます。
10.土砂災害特別警戒区域に指定された土地の評価について
土砂災害特別警戒区域(通称:レッドゾーン)に指定された土地(宅地及び宅地の評価に準じた土地等)は、特定の開発行為や建築物の構造に対して制限を受けることから固定資産税課税上でも影響を考慮する必要があります。そのため、平成30年度課税から固定資産評価額に0.7の減価補正率を適用しています。
ダウンロード
- 相続人代表者指定(変更)届出書兼現所有者申告書 [PDFファイル/130KB]
- 家屋所有者変更届出書(相続) [PDFファイル/53KB]
- 家屋所有者変更届出書(譲渡) [PDFファイル/53KB]
- 納税管理人申告書 [PDFファイル/43KB]
関連リンク
外部リンク
- 「未来につなぐ相続登記」について(山口地方法務局)<外部リンク>