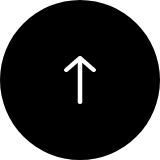本文
令和8年度保育所・幼稚園の新規・継続入所、無償化制度の手続について
保育所入所について
注意事項
- 次年度4月入所の申請期間は、11月4日(火曜日)から12月25日(木曜日)となり、例年より早い締切日となります。また、締切日以降は申請を受け付けることができません。次回受付は5月入所分(4月上旬受付)となります。継続入所を希望する方も同様に取り扱いますので、必ず締切日までに手続きしてください。
なお、急な転勤などの外的要因により入所が必要な場合は、町民福祉課児童係までお問い合わせください。 - 5月以降の年度途中入所は、入所希望月の前月1日から10日が申請受付期間となり、今回は申請できませんのでご注意ください。
- 申請する方は、配布資料に含まれる案内文や記入例をよくご確認ください。
概要
保育所は、保護者が就労や疾病などにより家庭以外での保育が必要な場合に利用する施設です。
次年度4月から新規利用または継続利用を希望する方は、以下の内容を確認して期間内に申請してください。
入所要件
保護者が、次の「保育が必要な事由」のいずれかにより保育を必要としていること。
| 事由 | 基準 |
|---|---|
| 就労 | 1か月あたり48時間以上労働することが常態である |
| 妊娠・出産 | 出産前2か月後3か月である |
| 保護者の疾病・障がい | 疾病・負傷している 精神や身体に障がいを有している |
| 親族の介護・看護 | 親族を常時介護または看護している |
| 就学 | 学校、専修学校、各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学している |
| 求職活動 | 求職活動を行っている(起業準備含む)(注)有効期間3か月、短時間認定 |
| 災害復旧 | 震災、風水害、火災その他の災害の復旧にあたっている |
| 育児休暇取得中 (新規申請者は不可) |
すでに保育所に入所しており、育児休暇を取得している |
| その他 | 上記に類する場合で町長が特に認める場合 |
(注)入所希望時点で定員超過の場合、町の基準に基づき入所順位を決定します。
申請書類配布方法
- 新規利用の場合 町民福祉課児童係(1階3番窓口)で配布
- 継続利用の場合(町内保育所入所者) 保育所で配布
- 継続利用の場合(町外保育所入所者) 町から郵送
(注)申請書は、本ページからもダウンロードできます。
申請方法・申請先
下記の書類をすべて揃えて、町民福祉課児童係(1階3番窓口)へ提出してください。
- 保育申請書(2・3号用)
- 就労証明書など保育の必要性を証明する添付書類(父・母ともに必要)
提出が必要な書類は事由により異なるため、詳細は申込案内をご参照ください。
(注)就労証明書の内容の確認のため、田布施町から勤務先に直接連絡させていただく場合がありますので、ご了承ください。
(注)きょうだいの入所の場合、事由証明の書類は世帯で1部ご準備ください。保育申請書は子ども1人につき1枚ずつ作成してください。
申請期間
令和7年11月4日(火曜日)から令和7年12月25日(木曜日)まで
(注)町外施設の新規入所を希望される場合は、提出期限が自治体により異なります。お早目にご相談ください。
幼稚園入所について
概要
幼稚園の入所は、希望する施設で直接手続をしてください。施設が入所を決定します。
手続き後、町への支給認定申請が必要となりますので、町民福祉課児童係(1階3番窓口)で申請してください。
申請書類配布方法
- 新規利用の場合 町民福祉課児童係(1階3番窓口)で配布
- 継続利用の場合(町内施設利用者) 施設で配布
- 継続利用の場合(町外施設利用者) 町から郵送
(注)申請書は、本ページからもダウンロードできます。
申請方法・申請先
支給認定申請書(1号用)を、町民福祉課児童係(1階3番窓口)へ提出してください。
申請期間
令和7年11月4日(火曜日)から令和8年2月27日(金曜日)まで
(注)2月27日(金曜日)以降の申請も受け付けますが、年度内の認定が叶わない場合があります。
施設等利用給付認定について
概要
幼稚園の預かり保育、一時預かり保育、病児・病後児保育、ファミリー・サポート・センター、認可外保育施設等の利用者で、「保育所入所について」に記載の保育の必要性の要件を満たしている場合、利用料が払い戻されます(上限あり)。
なお、この無償化制度をすでに利用している場合も、現況確認のため毎年手続が必要ですので、必ず申請してください。
払い戻しの上限額
- 幼稚園等預かり保育
3~5歳児 月11,300円まで
満3歳児(注) 月16,300円まで - 認可外保育施設等
3~5歳児 月37,000円まで
0~2歳児(注) 月42,000円まで
(注)住民税非課税世帯のみが払い戻しの対象です。
申請書類配布方法
- 新規利用の場合 町民福祉課児童係(1階3番窓口)で配布
- 継続利用の場合(町内施設利用者) 施設で配布
- 継続利用の場合(町外施設利用者) 町から郵送
(注)申請書は、本ページからもダウンロードできます。
申請方法・申請先
下記の書類をすべて揃えて、町民福祉課児童係(1階3番窓口)へ提出してください。
- 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書
- 就労証明書など保育の必要性を証明する添付書類(父・母ともに必要)
提出が必要な書類は事由により異なるため、詳細は申込案内をご参照ください。
(注)きょうだいの利用の場合、事由証明の書類は世帯で1部ご準備ください。子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書は子ども1人につき1枚ずつ作成してください。
申請期間
令和7年11月4日(火曜日)から令和8年2月27日(金曜日)まで
(注)2月27日(金曜日)以降の申請も受け付けますが、年度内の認定が叶わない場合があります。
多子世帯利用給付認定について
概要
第2子以降の対象子どものうち、認可外保育施設、企業主導型保育事業を利用者で、「保育所入所について」に記載の保育の必要性の要件を満たしている場合、利用料が払い戻されます(上限あり)。
なお、この制度をすでに利用している場合も、現況確認のため毎年手続が必要ですので、必ず申請してください。
払い戻しの上限額
- 認可外保育施設
第2子以降の3歳未満児 月42,000円まで - 企業主導型保育事業
第2子以降の1、2歳児 月37,000円まで
第2子以降の0歳児 月37,100円まで
申請書類配布方法
- 新規利用の場合 町民福祉課児童係(1階3番窓口)で配布
- 継続利用の場合(町外施設利用者) 町から郵送
(注)申請書は、本ページからもダウンロードできます。
申請方法・申請先
下記の書類をすべて揃えて、町民福祉課児童係(1階3番窓口)へ提出してください。
- 多子世帯利用給付認定(変更)申請書
- 就労証明書など保育の必要性を証明する添付書類(父・母ともに必要)
提出が必要な書類は事由により異なるため、詳細は申込案内をご参照ください。
(注)きょうだいの利用の場合、事由証明の書類は世帯で1部ご準備ください。多子世帯利用給付認定(変更)申請書は子ども1人につき1枚ずつ作成してください。
申請期間
令和7年11月4日(火曜日)から令和8年2月27日(金曜日)まで
(注)2月27日(金曜日)以降の申請も受け付けますが、年度内の認定が叶わない場合があります。
ダウンロード
- 保育所申請関係書類一式 [その他のファイル/986KB]
- 幼稚園申請関係書類一式 [その他のファイル/356KB]
- 施設等利用給付認定書類一式 [その他のファイル/1.12MB]
- 多子世帯利用給付認定書類一式 [その他のファイル/759KB]