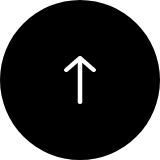本文
特定外来生物(動物)について
概要
特定外来生物(動物)とは、もともとその地域にいなかったのに、人間活動によって他の地域から持ち込まれた生物のうち、生態系・人の生命・身体・農林水産業へ被害をおよぼすもの、または及ぼすおそれのあるもので「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」(外来生物法)により、指定されている生物のことを言います。
現在、特定外来生物(動物)のうち、哺乳類に関しては、25種類指定されており、町内では「ヌートリア」が確認されております。
これらの特定外来生物は、飼養・保管・運搬・輸入といった取り扱いが規制されており、違反すると懲役や罰金といった罰則があります。
外来生物法の詳細や、特定外来生物の種類についての詳細は、下記のリンクから環境省のホームページをご覧ください。
ヌートリアについて


(注)町の有害鳥獣捕獲許可を得た方が捕獲した写真です。
南米原産の哺乳類で、ネズミの仲間です。体形はビーバーのようですが、体色は茶褐色で尾が長く、大きな前歯(オレンジ色)が特徴です。成長すると頭から胴までの長さが50~70cm、尾の長さは30~50cm、体重は6~9kg程度になります。泳ぎが得意で河川や湖沼などの水際で生活し、土手などに直径20~30cm程度、奥行き1~6m程度のトンネル状の巣穴を掘ります。戦時中の軍服の毛皮用、食用として導入されたものの、終戦と同時に飼育個体は野外に捨てられて野生化したもので、現在は西日本やその他の地域でたびたび目撃されています。水生や陸生の植物の葉や茎、根茎などを食べる草食性動物ですが、貝や甲殻類を食べることもあります。
町内では一部の河川などの水辺近辺で目撃されています。
基本的におとなしい動物ですが、追い詰められたり興奮すると、暴れたり長い爪で引っかかれることがあります。また、ヌートリアに限らず、野生動物は病気を持っていることがあるため、むやみに近づいたり捕まえないようにしてください。
外部リンク
環境省「日本の外来種対策」<外部リンク>