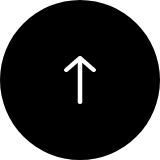本文
個人住民税の公的年金からの特別徴収制度について
公的年金からの特別徴収制度の概要
公的年金等を受給している方の「公的年金等の所得にかかる個人住民税(町民税+県民税)」の徴収については、「特別徴収」の方法によることとされています。
これは、公的年金等の支払を行う者(日本年金機構など)が、公的年金等の支払を行う際に個人住民税を差し引き(天引きし)、納税義務者(公的年金等を受給している方)に変わって市区町村に納入するものです。
この制度は、納税義務者の負担軽減や、市区町村における事務の効率化を目的として、平成21年10月から全国で導入されました。
特別徴収が行われる年金(特別徴収対象年金)
個人住民税の特別徴収が行われる「公的年金」とは、老齢または退職を支給事由とするものを指します。障害年金や遺族年金といった非課税年金からは個人住民税の特別徴収は行われません。
特別徴収の対象となる方
その年の4月1日現在において65歳以上の公的年金受給者で、前年中の公的年金等の所得にかかる個人住民税の納税義務のある方が対象となります。
ただし、次のいずれかに該当する場合、特別徴収の対象とはなりません。特別徴収の対象とならない方については、個人住民税を納付書や口座振替等により納めていただくことになります(普通徴収)。
- 特別徴収対象年金の年額が18万円未満である。
- 特別徴収対象年金の額から所得税、介護保険料、国民健康保険税(または後期高齢者医療保険料)を差し引いた年額が、特別徴収される個人住民税よりも少ない。
- 当該年度の属する年の1月1日以降、町内に住所を有しなくなった(転出や死亡等)。
- 介護保険料が公的年金から特別徴収されていない。
なお、特別徴収の対象となった方でも、年度の途中で特別徴収が中止される場合があります。詳細につきましては、「特別徴収が中止となる場合」をご参照ください。
特別徴収される税額と徴収方法
公的年金等から特別徴収される税額は、前年に支給された公的年金等(厚生年金、共済年金、企業年金等を含む)の所得に対する個人住民税(均等割額+所得割額)となります。
なお、個人住民税の課税対象となる公的年金等とは、老齢・退職を支給事由とするものを指します。障害年金や遺族年金に対しては課税されません。
前年度から引き続き特別徴収される方
前年度に徴収された税額の半分を、4月・6月・8月の年金支給時に3分の1ずつ徴収いたします(仮徴収)。そして、10月・12月・翌2月の年金支給時に、年税額から仮徴収された税額を差し引いた額を3分の1ずつ徴収いたします(本徴収)。
| 徴収方法 | 仮徴収 | 本徴収 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 徴収月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 翌2月 |
| 徴収税額 | 前年度の年税額の半分÷3 | (年税額−仮徴収税額)÷3 | ||||
| 3,500円 | 3,400円 | 3,400円 | 2,900円 | 2,800円 | 2,800円 | |
特別徴収における100円未満の端数は、仮徴収時のものは4月に、本徴収時のものは10月に端数全額が合算されます。
新たに特別徴収が開始される方
新たに65歳となられた方や、前年度中に年金からの特別徴収が中止となった方は、その年の10月の年金支給時から特別徴収が開始されます。
その年度の税額のうち半分を6月・8月に普通徴収の方法(納付書または口座振替で納付する方法)で納めていただき、残りの半分を10月・12月・翌2月の年金支給時に特別徴収いたします。
| 徴収方法 | 普通徴収 | 本徴収 | 翌年度の仮徴収 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 徴収月 | 6月 (第1期) |
8月 (第2期) |
10月 | 12月 | 翌2月 | 翌4月 | 翌6月 | 翌8月 |
| 徴収税額 | 年税額の半分÷2 | (年税額−仮徴収税額)÷3 | 前年度の年税額の半分÷3 | |||||
| 5,400円 | 4,000円 | 3,200円 | 3,100円 | 3,100円 | 3,200円 | 3,100円 | 3,100円 | |
普通徴収における1,000円未満の端数は、6月(第1期)に端数全額が合算されます。特別徴収における100円未満の端数は、本徴収時のものは10月に、翌年度の仮徴収時のものは4月に端数全額が合算されます。
特別徴収が中止となる場合
次のいずれかの事由に該当した場合、年金からの特別徴収は中止となります。
- 亡くなられた場合
- 他市区町村へ転出した場合(注)
- 年度の途中で個人住民税の額が変更となった場合(注)
- 年金の差止や失権により、特別徴収を行っていた年金自体が停止した場合
特別徴収が中止となった時点で未徴収税額がある場合、普通徴収の方法により納めていただくことになりますので、該当される方には通知をお送りいたします。
(注)平成28年10月1日以降、2(他市区町村への転出)及び3(個人住民税額の変更)については、一定の要件を満たす場合、公的年金からの特別徴収が継続されることがあります。