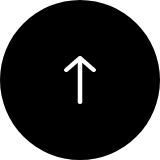本文
国民年金保険料について
老齢基礎年金を受けるためには、最低10年以上(保険料免除期間、合算対象期間(カラ期間)を含む)の保険料を納めることが必要です。40年間(480月)納めてはじめて満額の年金となります。
令和7年度の国民年金保険料
月額 17,510円
(まとめて前納すると割引が適用されます。)
国民年金保険料の納付について
納付書による現金納付・電子決済
国民年金の加入後、約1カ月ほどで納付書が届きます。保険料の納付期限は翌月の末日です。
コンビニエンスストアや金融機関の窓口でお支払いいただけます。田布施町役場では納付できませんのでご注意ください。
納付書のバーコードをスマートフォンの決済アプリで読み取ることによって、電子(キャッシュレス)決済もできます。
6カ月分・1年分・2年分の前納も可能です。前納する場合は割引があります。
| 納付の種類 | 納付額 | 割引額 |
|---|---|---|
| 毎月納付(翌月未納付) | 17,510円 | ー |
| 6カ月前納 | 104,210円 | 850円 |
| 1年前納 | 206,390円 | 3,730円 |
| 2年前納 | 409,490円 | 15,670円 |
クレジットカードによる納付
クレジットカードにより定期的に納付ができます。
納付額は納付書払いと同じで、6カ月分・1年分・2年分を前納することも可能です。
申込みは役場や年金事務所で受け付けています。
| 納付の種類 | 納付額 | 割引額 |
|---|---|---|
| 毎月納付(翌月未納付) | 17,510円 | ー |
| 6カ月前納 | 104,210円 | 850円 |
| 1年前納 | 206,390円 | 3,730円 |
| 2年前納 | 409,490円 | 15,670円 |
口座振替による納付
銀行口座から定期的に納付ができます。
6カ月分・1年分・2年分の前納や、60円値引きになる早割納付(当月末振替)もできます。
割引額は納付書やクレジットカードによる納付よりも多くなります。
申込みは役場、年金事務所、ご指定の金融機関で受け付けています。
| 納付の種類 | 納付額 | 割引額 |
|---|---|---|
| 毎月納付(翌月末振替) | 17,510円 | ー |
| 早割納付(当月末振替) | 17,450円 | 60円 |
| 6カ月前納 | 103,870円 | 1,190円 |
| 1年前納 | 205,720円 | 4,400円 |
| 2年前納 | 408,150円 | 17,010円 |
前納を希望する場合の申込み期限について
口座振替やクレジットカードによる前納の申込みはいつでも可能ですが、申込みの時期により前納対象期間は変わります。
付加年金制度
月々の保険料に加えて毎月400円を追加で支払うことで、将来の年金額に200円ずつ上乗せできる制度です。
口座振替やクレジットカード納付をしている方は、通常の保険料と一緒に引き落としされます。
保険料の前納をしている方は付加年金も一緒に前納できる上、割引もされます。
申込みは、役場や年金事務所で受け付けています。
国民年金保険料の免除(納付猶予)について
国民年金保険料の免除(納付猶予)とは
保険料を納付が経済的に困難な場合に、申請して承認を受けることで保険料の納付が免除または猶予される制度があります。
保険料を未納のままにしておくと老齢基礎年金や障害基礎年金を受給できないことがありますので、納付が困難な場合には必ずご相談ください。
全額免除、一部免除(4分の3・半額・4分の1免除)
本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定以下の場合には、保険料が免除されます。
免除制度には全額免除のほか、4分の3免除、半額免除、4分の1免除などの一部免除もあります。
申請時点から最大2年1か月前まで遡って申請することができます。
申請は原則として毎年度必要です。ただし、全額免除の承認を受けた場合で、翌年度以降も全額免除の申請を希望する場合は、継続して申請があったものとして審査(継続審査)を行います。
ただし、後述の「離職による特例免除」によって全額免除の承認を受けた場合は、翌年度も申請が必要ですのでご注意ください。
なお、学生納付特例制度の対象となる方は、この免除を受けることはできません。
納付猶予制度
50歳未満の方で、本人及び配偶者の前年所得が全額免除の基準に該当すれば、保険料の納付を猶予することができます。
申請時点から最大2年1か月前まで遡って申請することができます。
申請は原則として毎年度必要です。ただし、納付猶予の承認を受けた場合で、翌年度以降も納付猶予の申請を希望する場合は、継続して申請があったものとして審査(継続審査)を行います。
ただし、後述の「離職による特例免除」によって納付猶予の承認を受けた場合は、翌年度も申請が必要ですのでご注意ください。
なお、学生納付特例の対象となる方は、この制度の対象外となります。
学生納付特例制度
学生の方で本人の所得が半額免除の基準に該当すれば、保険料の納付を猶予することができます。
申請には『学生証の写し』または『在学証明書(写し不可)』の添付が必要です。
学生納付特例は、申請日に関わらず、4月から翌年3月まで(申請日が1月から3月までの場合は前年4月から3月まで)の期間を対象として審査します。申請時点から2年1カ月前までの期間についても、遡って申請することができます。
なお、「学生」とは大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校、各種学校、一部の海外大学の日本分校に在学する方で、夜間・定時制課程や通信課程の方も含まれます。この制度の対象とならない学校等もありますので、ご不明な場合は年金事務所にお問い合せください。
離職による特例免除
離職により保険料の納付が困難な場合は、離職した方の『雇用保険受給資格証』または『雇用保険被保険者離職票』の写しを添付することで、離職した日の翌日の前月から翌々年度の6月までの保険料については、離職した方の所得を無いもの(0円)とみなして免除(納付猶予)の審査が行われます。
免除等の基準について
免除の承認を受けるためには、申請者本人、配偶者、世帯主の所得が次表の「免除等が承認される所得の基準額」以下である必要があります。
配偶者は申請者本人と別世帯であっても審査の対象となります。
なお、納付猶予の場合は申請者本人とその配偶者が、学生納付特例の場合は申請者本人のみが審査対象となります。
| 免除種別 | 免除等が承認される所得の基準額 |
受給資格期間への |
老齢基礎年金への 反映額 |
|---|---|---|---|
| 全額免除 | 67万円+(35万円×扶養親族等の数)(注1) | 算入される | 2分の1 |
| 4分の3免除 | 88万円+扶養控除額+社会保険料控除額 |
算入される |
8分の5(注2) |
| 半額免除 | 128万円+扶養控除額+社会保険料控除額 | 8分の6(注2) | |
| 4分の1免除 | 168万円+扶養控除額+社会保険料控除 | 8分の7(注2) | |
| 納付猶予 | 67万円+(35万円×扶養親族等の数) | 算入される | 反映されない |
| 学生納付特例 | 128万円+扶養控除額+社会保険料控除額 |
(注1)地方税法に定める障害者・寡婦・ひとり親である場合、所得の基準額が135万円となります。
(注2)免除後の月額保険料を納付した場合のみ算入・反映されます。納付が無い場合は未納と同じ扱いとなります。
保険料の追納制度
老齢基礎年金の年金額を計算するときに、保険料の免除(納付猶予)期間がある場合には、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が低額になりますが、免除(納付猶予)期間が過去10年以内であれば保険料の追納を行うことができ、老齢基礎年金への反映額を増やすことができます。
保険料を追納する場合は最も古い月分からとなります。また、免除(納付猶予)期間の翌年から起算して3年度目以降の追納は、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
国民年金保険料の法定免除について
国民年金第1号被保険者が法律で定められた次の要件に該当した場合、届出により国民年金保険料の納付義務が免除されます。
過去に遡って要件に該当した場合、その期間における納付済の国民年金保険料は返還されます。
なお、要件に該当しなくなったときにも届出が必要です。
| 要件 | 免除が開始となる月 |
|---|---|
| 生活保護の生活扶助を受けている | 生活保護を受け始めた日を含む月の前月の保険料から |
| 障害基礎年金・被用者年金の障害年金(2級以上)を受けている | 認定された日を含む月の前月の保険料から |
| 国立ハンセン病療養所などで療養している | 療養が始まった日を含む月の前月の保険料から |
産前産後期間の国民年金保険料の免除について
国民年金第1号被保険者が出産した場合、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。
この場合における「出産」とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産のことをいい、死産、流産等も含みます。
免除期間は、出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間(多胎出産の場合は属する月の3カ月前から6カ月間)です。
なお、産前産後期間は付加保険料の納付ができます。
出産予定日の6カ月前から届出が可能で、出産後でも届出できます。
既に国民年金保険料免除や納付猶予、学生納付特例、法定免除が承認されている場合でも届出が必要ですのでご注意ください。(産前産後免除は通常の免除や納付猶予、学生納付特例、法定免除よりも優先されるため。)
産前産後期間として認められた期間は、保険料を納付したものとして将来の年金受給額に反映されます。