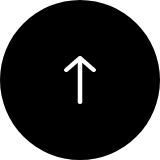本文
介護保険料
介護保険料について
65歳以上の人の介護保険料は3年ごとに見直しを行います。3年間で必要となる介護保険給付額から介護保険料を算定します。令和7年度から令和8年度の介護保険料は下表のとおりで、前年の所得内容と世帯の課税状況に応じて保険料額が決まります。
介護保険料は介護が必要な高齢者とその家族を社会全体で支えていくための大切な財源です。皆さまのご理解とご協力をお願いします。
基準額の算出方法
令和7年度から令和8年度の基準額は次のとおりです。
「田布施町で必要な介護サービスの総費用」×「65歳以上の方の負担分(約23%)」÷「田布施町に住む65歳以上の方の人数」= 田布施町の基準額59,000円(年額)
町で必要な介護サービスの総費用は、2分の1を国・県・町が負担し、残る2分の1を第1号被保険者保険料(65歳以上の人)と第2号被保険者保険料(40歳から64歳の人)で負担します。
所得段階別介護保険料【令和7年度】
第1号被保険者の介護保険料は、「基準額」を基にして所得段階ごとに算出します。
| 対象となる方 | 保険料額(年額) |
|---|---|
| 住民税非課税世帯で、生活保護、老齢福祉年金(注)を受給している | 第1段階 16,800円 |
| 住民税非課税世帯で、前年の年金収入額と合計所得金額の合計から年金雑所得を引いた金額が80.9万円以下 | |
| 住民税非課税世帯で、前年の年金収入額と合計所得金額の合計から年金雑所得を引いた金額が80.9万円を超え120万円以下 | 第2段階 28,600円 |
| 住民税非課税世帯で、前年の年金収入額と合計所得金額の合計から年金雑所得を引いた金額が120万円を超える | 第3段階 40,400円 |
| 世帯に住民税課税者があり、本人は住民税非課税で前年の年金収入額と合計所得金額の合計から年金雑所得を引いた金額が80.9万円以下 | 第4段階 53,100円 |
| 世帯に住民税課税者があり、本人は住民税非課税で前年の年金収入額と合計所得金額の合計から年金雑所得を引いた金額が80.9万円を超える | 第5段階 59,000円 (基準額) |
|
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満 |
第6段階 70,800円 |
| 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満 | 第7段階 76,700円 |
| 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満 | 第8段階 88,500円 |
| 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満 | 第9段階 100,300円 |
| 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満 | 第10段階 112,100円 |
| 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満 | 第11段階 123,900円 |
| 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満 | 第12段階 135,700円 |
| 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上 | 第13段階 141,600円 |
平成30年度からは、長期譲渡所得または短期譲渡所得に係る特別控除がある場合、合計所得金額から控除します。
消費税率の引き上げに伴い、世帯全員の住民税が非課税である人(第1段階から3段階)を対象に介護保険料の軽減を強化しています。
(注)明治44年4月1日以前に生まれた人、または大正5年4月1日以前に生まれた人で一定の条件を満たしている人が受給している年金です。
納付方法
1.年金天引き(年金が年額18万円以上支給されている人)
保険料の年額を6回に分けて年金の支払い時に差し引かれます。
ただし、次のような人を除きます。
(1)年度途中に65歳になられた人
(2)年度途中に転入された人
(3)年度途中で所得段階区分が変更(減額)になられた人
(4)年金受給権を担保にされている人
(5)年度途中で基礎年金番号を変更された人
(6)老齢福祉年金のみ受給されている人
(7)老齢基礎年金の受給繰り下げを行い、老齢厚生年金のみ受給されている人
2.年金天引き以外の人(納付書もしくは口座振替による納付)
町から送付する納付書や口座振替により納めていただきます。
(1)納付書による納付
次の指定金融機関や役場の会計窓口で納めていただきます。
- 山口銀行
- 西京銀行
- 東山口信用金庫
- 山口県農業協同組合
- 広島銀行
- ゆうちょ銀行・郵便局(中国地方5県内に限ります)
- 北九州銀行
- 田布施町役場会計室
(2)口座振替による納付
登録されている金融機関の口座から各期ごとの自動引き落としにより、納めていただきます。
口座振替を行うには金融機関で申請が必要です。
介護保険料の納め忘れにご注意ください
介護サービスを利用する場合は、所得に応じて1割・2割・3割の負担で利用できますが、保険料を滞納しているとその期間に応じて、次のように制限されます。
- 1年以上滞納すると支払い方法が変更されます。
介護サービスを利用したとき、いったん利用料の全額を自己負担し、あとから申請に基づき負担割合に応じて9割分・8割分・7割分を支給します。
また、1年6か月以上滞納すると、「保険給付の一時差止」が行われ、さらに「差止保険給付額から滞納保険料の控除」が行われます。 - 2年以上滞納すると給付額が減額されます。
介護保険料を滞納している期間に応じて、一定期間、本人の負担割合が1割または2割から3割、3割から4割に引き上げられます。また、高額介護サービス費などの支給が受けられなかったり、食費・居住費(滞在費)の減額が受けられなくなります。
納付について困ったときは、早めにご相談ください
保険料を滞納していると、介護サービスの利用が不利になるだけでなく、財産の調査や差し押さえを受ける場合があります。
災害などの特別な事情がある場合は、保険料の減免や徴収猶予を受けられることがあります。
詳細は、健康保険課賦課徴収係までお問い合わせください。